今回はプレゼンテーション。お客様からプレゼンテーションに依頼を受けたり、何かの商品販売のプレゼンテーションを作らなければならない時に、慣れてない人はちょっとひるみますよね。結局、過去に作成したいろんな資料をくっつけ、削って、なにとか作成してお客様で資料出したら、宛名が引用した資料のお客様名だった。。。なんて失敗いくつも見ました。(頼むよ。。。。)
今回はプレゼンテーションの中でも資料作成編として、書いてみます。
製造メーカーのためのプレゼンテーション
プレゼンテーションツール
プレゼンテーション資料の目的は『自社の製品を販売する』ために使用する重要なアイテムです。資料の作りやすさやアニメーションの充実さから作成ツールはパワーポイントを利用したものが多く、最近は動画のコンテンツも増えているので、客先でYoutubeサイトを経由してプレゼンテーションする場面も増えています。
本日はプレゼンテーションの構成がメインなのでツールについては紹介程度にしておきますが、パワーポイントにもかなり飽きがきている方々には下のようなプレゼンツールも面白いのではないかと思います。
1)Prezi(プレジ)
はじめてPreziで作成されたプレゼンを見た時は衝撃的でした。その動きのダイナミックさと動画に近いアクションはパワーポイントでは到底表現できないもので、最初は動画だと思ったぐらいです。私はまだ使用したことがないのですが、Preziのサイトに、恐らく製作者がアップロードしたコンテンツが無数に掲載されているので是非、一度この動きを体感してみて下さい。特にアップロードサイトには同じテンプレートを使用したいろいろな作品があるので、『おー、同じテンプレでこういう風に違うものができるんだ』と感心します。またテンプレートも日本ではあまりお目に掛かれないPOPで訴求力の強いフォームになっており、聴衆へのインパクトも非常に大きいと思います。
もちろんテンプレートを使用しないで一から作成することもできるようですが、その作成画面が1枚の紙にプレゼンテーションを、どんどん広げて書いていくイメージです。どこかで一回使ってみたいツールです。しかし目立つ特徴的なツールなのでプレゼンでテンプレート被ったら恥ずかしいですね。
2)Googleスライド
パワーポイントで資料作成していると、結構課題になるのが更新です。例えば、お客様に合わせて一部変更して使用する際に『このページ、こうした方が話しをしやすいな』と思い、ちょっと更新したりするのですが、だんだんどれが最後に作成したものかわからなくなったりします。また、プレゼンの骨格だけ作成して、ページの中の詳細な数値などはチームメンバーに頼むときも、メールでのファイルのやり取りになるのですが、お互いに複製のファイルがたくさん作られ、一応ファイル名は変更しないように指示をするのですが、なかなか徹底できないので苦労します。
Googleスライドはクラウド型で作成した資料がサーバー側に自動保存されるので、このような共同作業や、更新時の共有に便利だと思い、パーソナル版のお試しでテスト運用したことがあります。パワポのデータもフォントが少し変わってしまう時がありましたが、概ね読み込めますし、携帯などの端末にもフレキシブルに対応できるのがいいですね。パワポだと、ソフトで開かない限り表示がめちゃくちゃになるので、わざわざPDFにしてから送るのが通例だったのでこれはいいと思っていたのですが、無料版は作成したデータが公開されるようなことが書いてあったため(ちょっと真偽はさだかではないのですが)、実使用に移すのはやめてしまいました。
さて、私は今、更新問題を解決するためにスライドの右上に、wordのフィールドコードを使ってパワポの各スライドの右上に貼付け、更新をかけることで日時をアップデートしています。フィールド内の日時は保存では自動更新はしないので、更新をかけることを忘れてしまうと結局ダメなのですが、それでも、最近では保存と同時にフィールドの更新をすることが習慣になってきたので、本当にパワポの更新管理が楽になりました。私にとってはページごとに更新日時がアップデートされる機能があるプレゼン資料が一番欲しいですね。
フィールドコードの使い方を教えてくれた私にとって神サイト
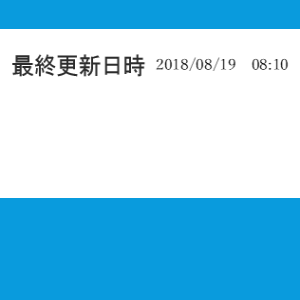
プレゼンテーションの構成
この他にも Slides や Microsoft社のSway、もちろんマックユーザー御用達のKeynoteなどがありますが、どれもテンプレートが充実していて、より短時間で美しいプレゼンテーション資料を作成することにおもむきを置いているツールです。
実はこれが私のプレゼンテーションのコンセプトと真逆なんですよね。私は、慣れてくるにしたがって、よりシンプル、スライドは抽象概念だけでいいという立てつけにしてることが多いですね。私はセミナーなどで話をすることも多く、まだまだ対面でのビジネスにこだわりがあるので『言葉の力』でプレゼンテーションを進めたい派でして。。。(資料作成に手を抜こうとしている訳ではないのですが、私もパワポのアニメーションにやや飽きてきている一人です)
さて、そろそろ本題に入りましょう。私のブログは基本、BtoB系企業の製造メーカーを意識していますので、これらの企業のプレゼンテーションのパターンからお話します。商品紹介のプレゼンとなった場合はさすがに抽象概念だけではどうにもならないですよね。最近では対面でプレゼンを行えないことも多く、デジタルマーケティングのコンテンツとして使用していくとなれば、それなりの工夫が必要になります。
1)開発背景
2)製品開発コンセプト
3)製品特性・スペック
4)それぞれの新機能の特徴
5)前製品との比較
6)競合製品との比較
7)終わりに
まぁ、製造メーカーのプレゼンテーションのアジェンダってこんな感じじゃないですか?図面や表などを使い、自社製品がいかにすごい商品であるのかを、長々と説明していく感じですね。ちなみに私の会社のプレゼンテーション資料もちょっと前まではこんな感じでした。笑い話ですが、スペックの競合比較スライドに、自社製品が不利な項目まで記載されているという技術者目線の資料です。
冒頭に戻りますが、プレゼンテーション資料の目的は『自社の製品を販売する』ために使用する重要なアイテムなので販売に繋がらない情報は不要です。ここをまずズラしてしまってはダメです。
上記のアジェンダを見た時にお客様の興味はどこになると思いますか?恐らく、聞いている振り!?をしながらし、頭の中では『うちの会社でどのくらい収益が見込めるのか?』、『いくらなのか?』なんてことを考えています。お客様の聞きたいこと(顧客価値)は製品の品質やコンセプトの良さではなく、この製品はうちの会社にどうのような収益をもたらしてくれるんだろうなんです。
上記プレゼンの構成はまさにプロダクトアウト的で、ソリューションビジネスのパートで何べんも指摘した売り手が起点のビジネス(モノ売り)になってしまっています。ソリューションビジネスはあくまでも買い手が起点(コト売り)でなければなりません。
モノ売り、コト売りを理解するにはこちらを!

では、このようなプレゼンテーションがレビューされた時にどのように修正すれば良いでしょうか?対面のプレゼンテーションでも、デジタルマーケティングでも1枚目は重要です。特にデジタルマーケティングの世界ではリンクをクリックして2回以内のクリックで目的に辿りつけないとお客様は離れていってしまいます。
1)製品の効果・・・この製品が何をもたらしてくれるのか?を1枚に訴求
2)ROIの訴求・・・効果を具体的な数値にして投資対効果(どのくらいで元が取れるのか?)を説明
3)導入事例・・・この製品で良い効果がでたユーザー事例
4)製品説明・・・お得意のやつです。
5)納期と工期、価格・・・デジタルマーケティングの場合、価格は載せずお問合せへ誘導
6)おわりに・・・最後に強いメッセージで購入意欲を後押し!
まずはつかみですね。その製品がうちの会社に何をもたらしてくれるのか、どんな課題を解決してくれるのかを最初(のページ)で伝えます。これが買い手起点(モノ売り)の提案です。その後重要なのは費用対効果(ROI)の提示です。この製品でどれくらい収益が上がるのか、コストがどれくらい下がるのかを導入前後で比較して経済価値(お金)で訴求することです。
更に追い打ちをかけるように導入事例です。お客様は売り手に対し、若干疑心を持っています。これを融解するのが実際に導入したお客様の事例です。『なるほど本当にうまくいっているところがあるのね』と思わせることで、この疑心が消えていきます。
この後は、製造メーカー得意の製品説明です、詳細なスペックを説明しようが、競合や旧製品との違いを説明しようが自由です。疑心のとれたお客様であれば素直に、効果的に入っていくでしょう。
納期、工期、価格は最後ですね。プレゼンテーションの内容が的を射たものであれば、お客様の購買意識はかなり高まっているので、具体的な導入に関する事項は最後に入れます。交渉が入るような製品については、価格をスライドには記載せず口頭になりますね。また交渉のできないデジタルマーケティングのコンテンツではお問合せフォームに誘導するのが良いでしょう。
最後は、強いメッセージと『購入したらこんなことが実現できます』といった購買の後押しを入れ込み、5~6枚で仕上げることが重要です。長いプレゼンはご法度ですね。
いかがでしょうか?これはマニュアルがある訳でもなく、私の経験から現時点で一番良いと思う構成をご紹介させて頂きました。実はこの流れのネタは 通販番組 なんです。日曜日にCSとかでずっと放送されている 通販番組。『一週間で10kgやせる!』とか『3か月で英会話がマスターできる!』というやつですね。最近はYoutubeの広告でもおなじみですが、それらのコンテンツにはプレゼンテーションの全てが詰まっています。皆さまも一度、半日ぐらい見続けてみるもの勉強になりますよ。では、また次回!ごきげんよう!



コメント